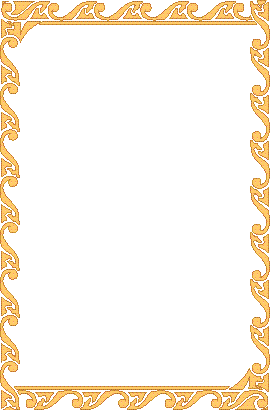
「 育つためのの土台 5 「触覚」 」
今月は触覚いわゆる皮膚刺激についてお話ししましょう。
皮膚刺激というのは場所によって脳への刺激量が違います。その場所の違いとは、日頃外に露出している部分と露出していない部分の違いです。これは服を着ていることで起こる事で、手や足が感じる感触が日頃露出していない腹や背中では、同じ物に接触した時に手足の数倍の刺激が脳に届きます。例えば風呂に入る時に服を着ていた時に感じる外気温が、裸になった時には服を着ていた時以上にしっかり外気温を感じます。それは外気温を感じる皮膚の量(面積)が増えたことが理由です。このことで脳への刺激量が増え脳が活性化するのです。特にこういった温度差というものは皮膚刺激にとっては非常に大きな影響力を持っているのです。よってこの温度差というものが生活からなくなると脳への刺激が減り、脳の活動が弱くなり子どもの場合はいろんな発達に影響を及ぼしてしまうのです。
余談的な話ですが、家庭内で飼われている犬や猫が一年中エアコン等で同じ温度の中で生活すると本能的に備わっている毛替えをしなくなり、いろんな病気を発症すると云われています。これは温度差が動物の生命に大きな影響力を持っているということですし、脳への刺激量の不足は動物の生存力すら弱めてしまうということなのです。
また人間界においても最近発汗の悪い子も増えています。汗は子どもの代謝に欠くことのできない身体機能です。この汗は人間の体温調節能力の貴重なセンサーなのです。このセンサーが鈍くなるといろんな病気の発生の引き金になります。よって寒い、暑い、ちょうど良いの3つの温度の組み合わせとバランスが子どもの生活には必要なのです。
ついでに言えば、我が園で子どもたちに靴下をはかせないことや、外遊びをはだしでさせる事も、足裏からの脳への刺激の重要性に基づいて行っている活動なのです。
また、最近「くる病」の乳幼児が増えています。それは日光を直接浴びる機会が少ない生活が原因と言われています。暑さのせいやマスコミの皮膚がんの恐れ等の報道が理由で日焼け止めクリームや全身を包むような服での散歩が直接日を受ける機会の減少が原因と思われます。
親が子の健康を考えればこそ日焼けさせないようにとの親心はわかりますが、子の成長発達の為に必要な活動をなくしてはいけません。
親が子どもを守るという大原則は、全てで大人と同様の生活をさせることではなく、子どもは現在発達途上なのだからという意識を持って、子どもの脳の活性化のために子どもだから必要な環境を与えることが必要です。そしてそれをする為にどういった環境が必要なのか是非勉強していただきたいと思っております。
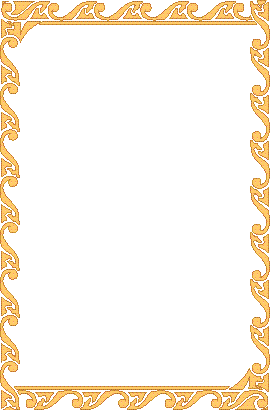
このコラムは、我が園の「園だより」に園長が書き続けている子育て講座の一部です。。
